|
■ NATM
NATM
「ナトム」と読んで/呼んでいます。
New Austrian Tunneling Method の頭文字を用いています。
新しい,オーストリアの,トンネルを掘る,方法(理論),なのですが、
これでは何だかさっぱりわかりません。
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1950年頃、オーストリアで考え出された理論です。
1962年に、専門の学会で「NATM」として提唱されました。
1960年代には、ヨーロッパに広まりました。
日本でも1960年代中頃には、実際のトンネル工事に試験導入されたそうです。
国内の本格的な導入(採用)は、それから数年後の70年代になってからです。
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
トンネル工事は、技術的な観点から次のように分けることができます。
・地山(地盤/岩盤)を「掘る技術」 (地山:じやま)
・掘ってできた空間を「支保する技術」 (支保:しほ)
『NATM』の最大の特徴は、「支保する技術(理論も含む)」に、
・吹付コンクリート と
・ロックボルト を用いる、という点です。
掘る技術には、
・削岩技術 [発破掘削/機械掘削]、
・ずり処理技術 [レール方式/タイヤ方式など] が含まれます。
物的な機械類や設備類そのものと、それをいかに使うか、という技術です。
支保する技術には、
・支保工(しほこう)技術 [吹付コンクリート/ロックボルト/鋼製支保工]、
・覆工(ふっこう)技術 が含まれます。
・当然、掘った地山を崩れないように支えて保つことが最重要課題ですので、
掘削断面の分割という技術 も含まれます。
どのようにしたら崩れないか、どうすればつぶれないか、という技術(理論)でしょう。
最大の特徴が示すとおり、どちらかと言えば『NATM』は、
「支保する技術」,「支保する理論」となるのではないでしょうか。
『NATM』と表現するとき、大きくふたつの意味があります。
ひとつはトンネルの「理論」、もうひとつはトンネルの「施工技術」、となります。
・研究者/識者の方々は、思い(思考・思想)という意味で、すなわち「理論」としてとらえる。
・工事に携わる方々は(私も含めて)、かたち(形式・形態)という意味で、
すなわち「施工技術(やり方)」としてとらえる。
といった表現になるのではないでしょうか。
私見ですが、単に『NATM』といった場合は、「NATM理論」が該当します。
「NATM工法」といった場合は、トンネル掘削工法の「NATM」が該当します。
ただ、トンネル工事に携わる者の間では、「NATM工法」ではなく、
単に「NATM」と呼ぶことが多いのです。
このサイト/ページでは、「施工技術(やり方)」としての「NATM工法」を扱っています。
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
『NATM
』は、ヨーロッパ(ヨーロッパアルプス)で考え出された工法(理論)です。
当時、日本では、「支保する技術」(支保工技術)の主流を占めていたのは、
「木製支保工(もくせいしほこう)」でした。
掘った部分が崩れてこないように、
板材(矢板:やいた)を当て、材木(丸太など)でツッパリをしていたのです。
崩れようとする地山の力が強ければ強いほど、たくさんの/厚い/太い木材が必要でした。
あるときは、その力に木材が耐え切れず、つぶれてしまうこともあったそうです。
1960年頃から、材木より強い(強度がある)鋼製の支保工が、用いられるようになりました。
戦後の復興で、鉄が容易に入手できるようになったことや、
鉄を冷間(熱しないでそのまま)で曲げる技術が向上したなどの、時代背景があります。
主に、H形鋼(エッチがたこう)と呼ばれる鋼材の一部分を円形に曲げ、
それを組合わせてアーチ状の「鋼製支保工(こうせいしほこう)」としていました。
ですが、掘った部分に板材(矢板)を当てる手法は、そのまま継続していました。
矢板の当て方によって、
掛矢板(かけやいた),送り矢板(おくりやいた),縫地矢板(ぬいじやいた)などの
分類をしていました。
掘削断面の分割の方法や、削岩やずり処理の方式、覆工の手順なども、
それぞれ特殊性を持っていました。
鋼製支保工と矢板の組合わせによる掘削工法を、『矢板工法』と呼びます。
国内に『NATM工法』が普及するまでに掘られたトンネルは、
ほとんどが「矢板工法」を採用しています。
このことにより、時間が経過した現在、多くの問題が発生しつつあります。
『NATM工法』と
『矢板工法』との対比を、簡単な図で表してみます。
|
NATM工法と矢板工法との対比 |
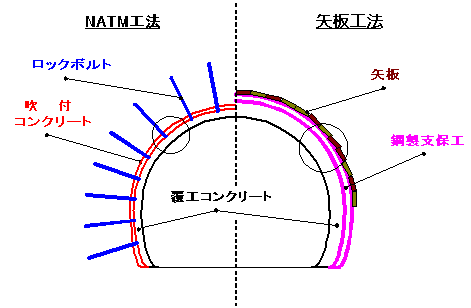 |
|
↓上図○印部の拡大イメージ |
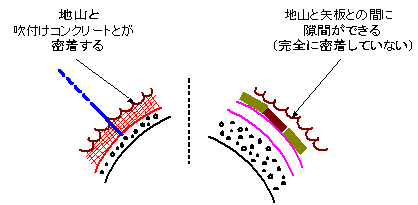 |
| |
|
|
鋼製支保工のイメージ |
矢板の設置イメージ |
 |
 |
また、鋼製支保工と矢板のイメージをつかんでいただきたかったため、
参考写真をアップしてあります。
実際は、矢板工法の鋼製支保工と矢板ではありませんので、ご了承ください。
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
日本は、地質学上、その生い立ちが変化に富んでいます。
そのため、地形・地質が複雑になっています。
ヨーロッパアルプスは硬く均一な地質、
日本国土は硬軟,脆弱(ぜいじゃく)とりまぜた複雑な地質、とイメージしてください。
硬い岩盤を「支保する技術」,「支保する理論」の『NATM』が、
ヨーロッパで生まれたこともうなづけます。
今や山岳トンネル工法では、あたりまえに採用される『NATM工法』です。
国内導入以来、四半世紀、その『NATM』を複雑な地質でも施工できるように、
様々な工夫が施されてきました。
現在でも、日本の地質に適応できるよう、改良/アレンジが続けられています。
日本の研究者/識者,工事に携わる人達により、
育てられてきた(今後も育つ)技術/理論なのです。
ヨーロッパで生まれ、日本で育った世界に誇れるトンネル技術。
それが、日本の『NATM工法』ではないでしょうか。
|