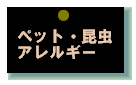
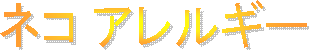

国内の一般家庭におけるネコ飼育率は約8%、喘息児のいる家庭では約7%という
統計結果(1995)があり、ほとんどが室内で飼育されていて、「外ネコ」はわずかである。
ネコの主要アレルゲンは、Fel d 1と呼ばれ、主には皮脂腺で産生し上皮・体毛(中でも顔・首・腋窩・尾の付け根に多い)の表面に蓄積される。また唾液、涙、尿、肛門嚢分泌物にも含まれる。産生は男性ホルモンにより増強される。
換気回数の少ない一般家屋では約25%が直径2.5μ以下の小粒子(下気道に容易に到達する)として空中に浮遊し、掃除機をかけるなど空気の攪拌によってより大きい粒子も舞い上がり、数時間にわたり空中に漂い続ける。また壁面への付着も少なくない(ダニアレルゲンは、より早く落下し、付着はほとんどが水平面)。
ネコ飼育家庭の塵埃中抗原量は、非飼育家庭の1000倍以上。またFel
d 1はネコが立ち入らない学校(飼育家庭数に比例)・デパート・バス座席などにも存在するが、これはネコ飼育者の衣服に付着して持ち込まれるからである。このため、あるいは訪問先のネコに遭遇することにより非飼育家庭の喘息児も6歳までに約半数がネコに感作される結果となる。
以上のように、ネコアレルゲンはネコのいる家庭内に高濃度に存在し、掃除機や空気清浄機で取り除ける性質のものではないので、ネコ喘息を発症した場合の基本的な対策はネコとの別居以外にはないといえる。妥協策として、相互に空気の流通がない「離れ」に暮らす方法も考えられるが、居住エリア周辺をネコが徘徊したり、ネコに接触した者が頻繁に出入りするようだと発作軽減効果はあまり期待できない。したがって、アレルギー症状をおこさないように安全にネコを飼育する方法は現状では存在しないといえる。
様々な事情でネコと同居しながらネコ喘息(ないし皮膚炎)の治療を行う場合には、吸入ステロイド薬(皮膚炎にはプロトピック軟膏外用)の使用はまず不可欠である。不可逆的な気道のリモデリングを生じないように病状を良好に保っておくことができれば、現在外国で新しい免疫療法(脱感作療法)の臨床試験が始まっていることもあり、将来に希望をつなぐことができる。

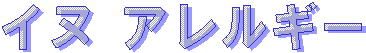
国内の一般家庭におけるイヌ飼育率は約17%、喘息児のいる家庭でも約17%という
統計結果(1995)があるが、ここ数年で和犬飼育が減り、洋犬が増え室内犬飼育率が急増した。
イヌの主要アレルゲンは、Can f 1と呼ばれ、皮屑中に認める。約20%が直径5μ以下の小さい粒子として存在し、空中滞留時間は長く、下気道に到達しやすい。またイヌが室内で活発に活動することによってアレルゲンを舞い上げ、壁面やカーテンなどに付着させる。 アトピー性皮膚炎で受診した乳児のうち、血清IgE(RIST)が高値である者の家庭で室内犬を飼育している場合、1歳の誕生日を過ぎないうちにイヌ皮屑RASTが陽性になる傾向がある。
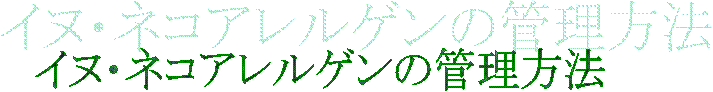
1. 喘息・アトピー性皮膚炎の患者さんの家庭ではペットを飼育しないことが原則である。
2. 特に室内での飼育は避けるべきである。現在室内にいるペットは戸外に出すようにすべきである。
3. どうしてもやめられない場合は、飼育場所を限定し、飼育場所から直接戸外へ24時間持続排気(換気)する。
4. 寝室・居間・子ども部屋にはペットを立ち入らせない。
5. ペットを世話する時には、専用の帽子・ガウンを用意するなど、普段の衣類とは別に扱う。
6. 衣類の素材はウール・フリースを避け、綿素材など静電気の発生しにくいものにする。
7. 寝具は月一回程度丸洗いする。経費節約のためには洗える布団・8kg以上の全自動洗濯機・乾燥装置の用意が必要。
8. 床・壁の拭き掃除を毎日行う。掃除機をかける際は(延長ホースなどを用いて)排気口を戸外に向け、窓を全開にして1時間以上換気をしておく。また換気扇は数時間以上運転しておく。花粉の飛散時期には夜間・早朝に行うようにする。
9. 家具・インテリアは、布製品・繊維の目立つものを避け、表面が滑らかなものにする。カーテンは表面の滑らかなロールカーテンに変更し壁面同様に拭き取りをする。普通のカーテンは週一回程度洗う。
10. ペットを週2回、シャンプーで洗浄する。(ペットのスキンケア用品が必要になるかもしれないので獣医さん等に相談を)
11. 雄ネコは去勢する。
12. 空気清浄機の効果は保障されたものがない。HEPAフィルターを使用したもので濾過後の空気の中で睡眠できるタイプのものが期待できる。
*
![]()
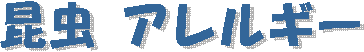
![]()
1 虫体の成分・糞を吸入することによって喘息や鼻炎を引き起こすものと、
2. 虫刺されに続いてアレルギー反応をおこすものがある。
1 虫体の成分・糞を吸入することによって喘息や鼻炎を引き起こすもの
屋外で繁殖するものとして蛾・ユスリカ、屋内ではゴキブリが重要なアレルゲンとして知られている。日本耳鼻咽喉科学会 昆虫アレルギー研究班(2001年5月発表)によれば、アレルギー性鼻炎のアレルゲンとして、IgE抗体保有率は蛾32.5%、ゴキブリ13.4%、ユスリカ16.1%であった。 これらは、喘息のアレルゲンとしてもほぼ同じ重要度がある。 したがって家庭内でのゴキブリ対策は重要である。 また、ユスリカによって明らかな喘息発作が生じる場合には、大量発生地域から他の土地へ転居することが必要になるかも知れない。
2.
虫刺されに続いてアレルギー反応を引き起こすもの
2-1.
蜂アレルギー 蜂に初めて刺された時には、蜂毒による刺激反応だけがおき、痛み・発赤が数時間みられる。2回目以降は、個人差があり、その感作の状況によって遅延型反応(刺された場所が翌日以降、徐々に腫れてくる)か、即時型反応(軽ければ蕁麻疹だけ、重症なら呼吸困難・血圧低下を伴い死の危険があるアナフィラキシーショック)を生じる。 スズメバチの群れに攻撃をうけると、アレルギーがなくても蜂毒により重篤な症状をきたすことがある。雑木林の近く、特に秋に被害を生じやすく、頭髪も含め黒い外観の衣類は避けるようにとされている。 アシナガバチは、住宅地・里山での被害が多く、洗濯物の中に入っていて刺されるケースが少なくない。スズメバチの毒と交差反応があるので、一方に感作されると他方のRASTも陽性になりやすい。 ミツバチは、養蜂家や農家、子どもが刺される機会が多い。花柄・白い服装、甘い香りの香水などを避けるようにとされている。 アナフィラキシーを起こしたことのある人には、いずれの蜂も命にかかわるので、生活上の注意は厳密に守られるべきである。 根本的な治療法である減感作療法は、一般の医療機関では行っているところはほとんどないが、当院では実施している。
2-2.
蚊アレルギー ヒトスジシマカ・アカイエカに刺された場合、乳幼児では遅延型反応のみ、学童期では遅延型と即時型反応の両方、青年期以降では即時型反応のみが生じる場合が多い。しかし青年期以降も、遅延型反応によって強い腫れや水疱を生じるケースもある。キャンプなど、刺される確率が高い場所にいく場合は、虫除け薬の塗布、超音波式蚊よけを準備していくべきである。遅延型反応で悩んでいる方には、漢方薬が有効なことが多い。
2-3.
ノミ刺症 ネコノミによるものが多い。下腿の下半分と足に集中して赤い丘疹や水疱がみられる。吸血時は無症状で、翌日以降に発疹が出る。
2-4.
ダニ刺症 ネズミにイエダニ、スズメ・ツバメにトリサシダニ、イエコウモリに寄生するコウモリマルヒメダニなどが、居室内に入りこみ、衣類の隙間に入って、痒みの強い赤い丘疹を主に体幹部に生じる。刺している場面を見ることはまずないが、家にこれらの動物が住み着いた際に発症すれば、原因として推定される。(ダニは昆虫ではなく、クモの仲間)
2-5.
ケムシ皮膚炎 梅雨頃に、椿やサザンカの葉を食べるチャドクガの幼虫が発生して被害が見られる。近寄ると多数の毒針毛をとばし衣類を貫通して皮膚に刺さる。アレルギーになっていると症状が強く、長引く傾向がある。