|
■ 安曇野は、ほんとに湖だったのか
『小太郎伝説』は、ロマンに富むとともに、先人の苦労を推し量る物語です。
それはそれとして、個人的に、『小太郎伝説』について、疑問を抱く点があります。
1.「犀川」は、小太郎親子によって切り開かれたのか
2.安曇野は、その昔、ほんとに湖の底だったのか
この二点です。
***** ***** ***** ***** *****
結論、先にありき、
地質学的/地球科学的にみて、この地方が湖だったことは考え難いようです。
日本列島,松本盆地の形成といった観点から、「湖だった」とは、立証が困難とされています。
ただし、この地方には意外な事実(?)がありますので、
後日、『信州は海だったのか』でアップロードを予定しています。
「犀川」の由来は、『小太郎伝説』にあるとおりでしょうね。
しかしながら、切り開いたのは小太郎親子ではなく、
自然の地殻変動によるものと河川による浸食活動によるものです。
犀川に沿う国道19号線を走ると、いたるところで、特異な地層を目にすることができます。
特に生坂村山清路周辺は、地層が垂直に近い状態になっている場所もあるほどです。
通常、地層は、長い年月をかけて水平に堆積して構成されています。
これが想像を絶する地殻のエネルギーによって、
相互にくっついたり、離れたり、ねじまげられたり・・・。
傾いたり、隆起したり、陥没したり・・・。
そうした影響に加えて、
低いところ低いところへと、脆弱なところ脆弱なところへと水(川)が流れ、
現在の犀川ができました。
こうやって結論付けてしまうと、『小太郎伝説』などどこかへいってしまいそうですが・・・。
***** ***** ***** ***** *****
♪♪ 槍で分かれた梓と高瀬、めぐりあうのが押野崎(おしのざき) ♪♪
『安曇節』の一節です。
幼少の頃、『小太郎伝説』とともに、「押野崎」の由来を聞きました。
湖を一望できる岬のように突き出た形をしていたから押野崎、というものでした。
明科町には、上押野(かみおしの),下押野(しもおしの)の地名が現存しています。
裏手の中山山地(なかやまさんち)を、通称、「押野山(おしのやま)」とも呼んでいます。
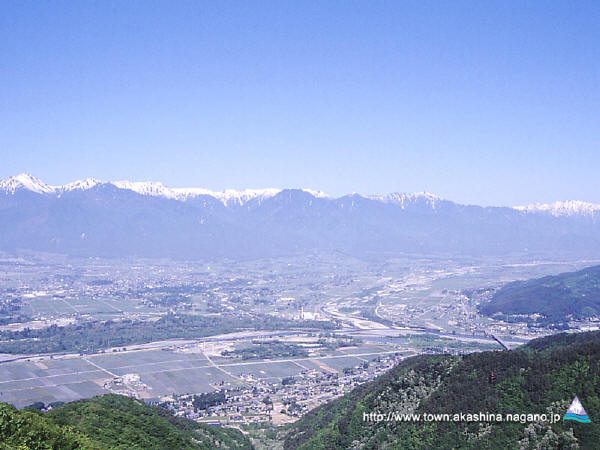
[ 明科町長峰山(ながみねやま)からの展望 《明科町ホームページより引用》
]
正面が北アルプス・安曇野。合流する河川が、右から、高瀬川,穂高川,梓川。
右下、犀川に架かる橋が犀川橋、その先が下押野・上押野、その右が押野山。
(※この写真の著作権は、明科町に帰属しており、使用にあたり許可をいただいております。)
『小太郎伝説』にあるように、仮に、生坂村山清路まで湖だったとすれば、
「押野山」は、確かに半島の突端のようでもあり、「押野崎」と言えたとも思います。
***** ***** ***** ***** *****
ふるさとの山に登り、悠久の歴史に満ちた安曇野を展望します。
伝説が語り継がれる地に生まれ、育ち、今後も生活していくであろう者としては、
ロマンや想像(妄想/瞑想)を、さらにさらに膨らませていきたいと思っております。
|